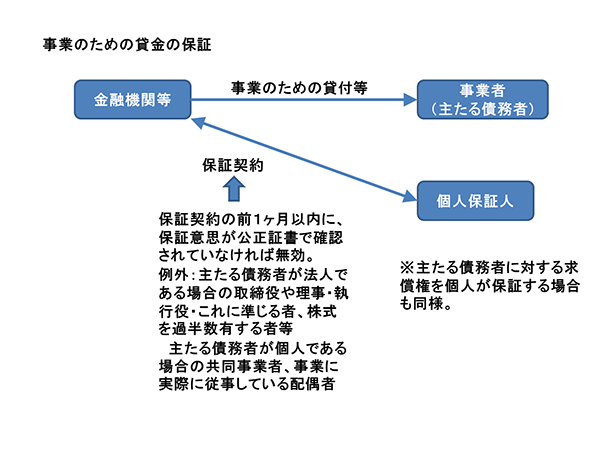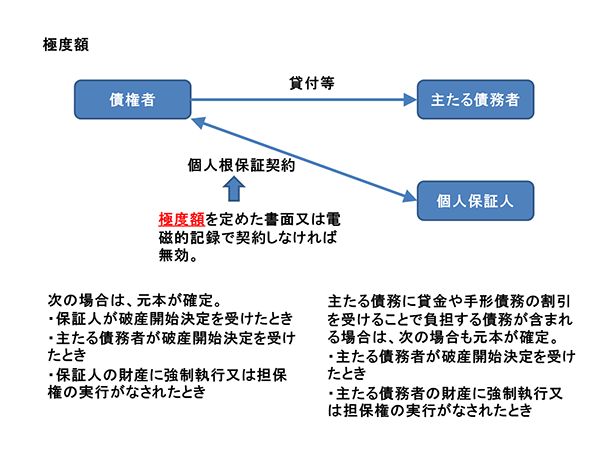民法改正(債権法改正)の重要ポイント 企業法務・民事再生の弁護士事務所 中島成総合法律事務所
企業法務・企業再生のためのリーガルサービスを目指します 中島成総合法律事務所
民法改正(債権法改正)の重要ポイント
第2 改正の重要ポイント
1 保証
- (1)事業のための貸金債務についての個人保証の制限
- (要綱仮案 第18、6、(1))(改正民法465条の6、465条の8、465条の9)
- 【ポイント】
- ア 事業のための貸金債務についての個人保証契約は、保証契約の前1ヶ月以内に、保証意思が公正証書で確認されていなければ無効となる。
- イ 事業のための貸金債務の保証人が有する、主たる債務者に対する求償権を、個人が保証する場合も、ア、と同様。
- ウ たとえ保証人となろうとする者が個人であっても、主たる債務者が法人である場合の取締役や理事・執行役・これに準じる者、株式を過半数有する者等が保証人となる場合は、ア、イ、は適用しない。
- 主たる債務者が個人である場合の共同事業者、事業に実際に従事している配偶者についても、ア、イ、は適用しない。
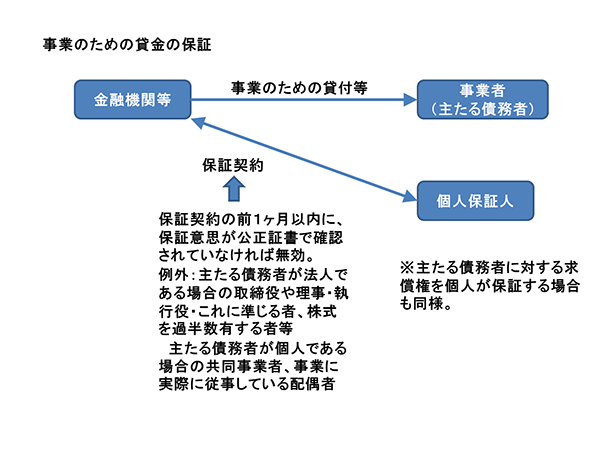
- 【改正の理由】
- 貸金債務についての個人保証の意思確認を厳格にすることで、保証人となろうとする者の保護を図る。
- 【影響等】
- 事業のための貸金債務の個人保証が禁止されたわけではない。また、一定の範囲の者については公正証書作成義務が課されない。
- 金融機関で個人保証を取る範囲が狭まっていき、特に公正証書が義務づけられる者の個人保証を取るケースは例外となると思われる。
- ※金融検査マニュアル
- 既に金融検査マニュアルにおいては、そのⅡ.1.(1).③.(ⅱ)(顧客の属性の確認)で、「個人連帯保証契約の場合にあっては保証人の経営への関与の度合い」の確認手続が必要とされ、これに関する欄外説明9、において「経営者以外の第三者と連帯保証契約を締結する場合は、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立するとの観点に照らし、必要に応じ「信用保証協会における第三者保証人徴求の原則禁止について」における考え方に留意することとしているか検証する。」とされている。
- (2)極度額の設定
- (要綱仮案 第18、5、(1)(2))(改正民法第465条の2、465条の4)
- 【ポイント】
- ア 個人根保証(不特定債務について個人が保証人となる保証)は、保証人が責任を負う最大額(極度額)を定め、かつ書面又は電磁的記録で契約されなければ無効となる。
- イ 個人根保証の保証人が保証する具体的な元本額は、次の場合確定する。
- ・保証人が破産決定を受けたとき。
- ・主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
- ・保証人の財産に強制執行又は担保権の実行がなされたとき。
- ウ 主たる債務に貸金や手形債務の割引を受けることで負担する債務が含まれている場合は、次の場合も元本が確定する。
- ・主たる債務者が破産決定を受けたとき
- ・主たる債務者の財産に強制執行又は担保権の実行がなされたとき
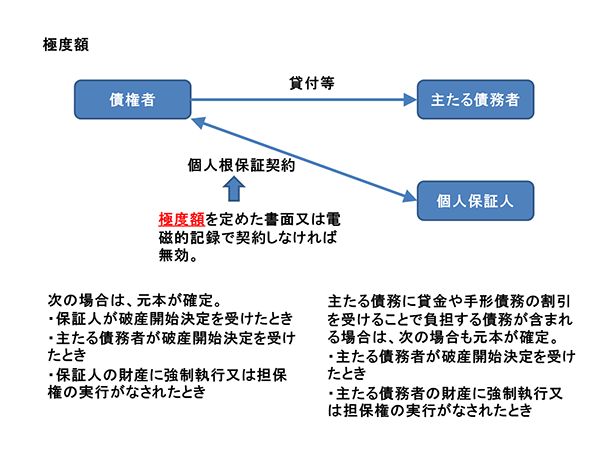
- 【改正の理由】
-
- 保証人保護のため、貸金債務等を個人が根保証する場合(貸金等個人根保証)は極度額を定めなければ無効となる等の改正が、平成16年に行われた。
今回の改正は、個人保証人の保護をより広い範囲で行うこととし、その他の保証、例えば賃貸借契約の個人保証等も個人根保証として対象とした。
- 【影響等】
- ア 極度額とは、元本、利息、損害賠償等、保証債務に関する全てを含んで最大限、保証人が負う可能性のある限度額のことで、確定した元本に対する遅延損害金が生じる場合であっても、その遅延損害金含めて最大限保証人が払うべき金額である。
極度額の大きさに明文の規制はない。しかし、保証の目的や保証人の資力などと比較して極端に大きな場合は、公序良俗違反として無効となる可能性がある。
イ、ウ 個人根保証で保証される具体的な元本額は、保証人が破産決定を受けたときには確定する。それ以降は、保証すべき元本は増額されなくなる。遅延損害金は発生し得るものの、元本と合わせて極度額の範囲でしか請求できない。
この点は、貸金等個人根保証とその他の個人根保証とで異なる。貸金等個人根保証は、主たる債務者が破産決定を受ければ元本は確定する。それ以上債務者が借りることを前提とする必要がないから。
保証人の財産に強制執行又は担保権の実行がされたときも元本が確定する。
他方、例えば、賃借人に強制執行等がなされても元本確定しない。賃借人の財産状況が悪化しても、賃料不払いなどによって信頼関係が破壊されない限り、賃貸借契約は続くから。
貸金等根保証では、主たる債務者に強制施行等がされても元本は確定する。
- ※元本と極度額の関係:元本として、例えば100万円が確定すると、その後遅延損害金がつくけれども、それがどれだけ増えても極度額以上の支払い義務を保証人は負わない。
- (3)保証契約締結時の情報提供義務
- (要綱仮案 第18、6、(2))(改正民法465条の10)
- 【ポイント】
- ア 事業のために生じる債務の個人保証を依頼するときは、債務者は、当該個人に対して債務者の財産や収支、債務の状況、担保として提供するものがあるか等を説明しなければならない。
- イ 債務者がその説明をしなかったり事実と異なる説明をしたこと(以下「不実の説明等」)によって個人が保証人となった場合で、債権者が不実の説明等があったことを知っていたか又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消せる。
- 【改正の理由】
- 事業のための個人保証人の保護。
- 【影響等】
- ア、イ 保証取消というドラスティックな制度の新設。
- 事業のための貸金債務の他、例えば、事務所や工場等事業に使う物件の賃貸借契約の個人保証人に対しては、賃借人に上記(3)ア、の説明義務がある。
-
不実の説明等がなされ、そのことを債権者が知ることができた場合などは、保証人は保証契約を取り消せる。
↓
新設規定で実務上重要な影響がある。保証人が、主たる債務者の不実の説明等を理由に保証契約取消を主張することが可能になるから。債権者は、不実の説明等がなかった、又は不実の説明等を知ることができなかったと主張することになる。
トラブルを避けるため、保証契約の際、「保証人は、主たる債務者から、その財産状況等について……の説明を受けたことを確認する。主たる債務者は、同内容が事実であることを確認する」等の書面が作成されるべき。
- (4)保証人の請求による情報提供義務
- (要綱仮案 第18、6、(3))(改正民法458条の2)
- 【ポイント】
- 保証人から請求があれば、債権者は、主たる債務の元本、利息、損害賠償、その他、主たる債務に関する全ての債務について、不履行の有無、残額、履行期限が過ぎているものの額を知らせなければならない。
- 【改正の理由】
- 保証人(個人保証人に限られない)の保護。
- 【影響等】
- この義務は、個人保証人からの照会に限られず、法人保証人からの照会も含む。主たる債務者の個人情報提供可能根拠として、照会元を個人保証人に限定しなかった。
この義務に違反しても直接の罰則規定はない。ただ場合によっては、照会に正確に応じなかったことなどによる損害賠償責任が問われる可能性がある。
- (5)期限の利益喪失についての情報提供義務
- (要綱仮案 第18、6、(4))(改正民法458条の3)
- 【ポイント】
- ア 主たる債務に期限の利益がある場合で、主たる債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は、個人保証人に対し、期限の利益喪失を知ったときから2ヶ月以内に、期限を喪失したことを通知しなければならない。
-
イ その通知を債権者がしなかったときは、債権者は、当該保証人に対しては、期限の利益喪失時から通知をするまでの間の遅延損害金を請求できない。
- 【改正の理由】
- 個人保証人の保護
- 【影響等】
- ア、イ 新設規定で、債権者が通知をしなかったときは、期限の利益喪失時点から通知を実際にしたときまでの間の遅延損害金の請求を保証人に対しては請求できない。注意を要する。
≪ 第1 改正経緯
改正の重要ポイント2 詐害行為取消権 ≫
目次へ戻る
企業法務・倒産法・会社の民事再生 中央区銀座 中島成総合法律事務所